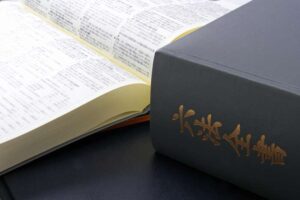税務調査は無制限に遡って実施することはなく、時効になれば申告誤りがあったとしても指摘されることはありません。
ただし時効までの期間は申告内容等によって異なり、最長10年前まで遡って調査が行われる可能性がありますので、今回は税務調査の対象期間と、実際の調査で対象となる範囲について解説します。
国税当局が処分できる期間は法律で定められている
税務署長には、国税債権を確定させる処分ができる権利(賦課権)が与えられていますが、賦課権には期限が定められています。
期限は申告内容等によって異なりますので、ケースごとの除斥期間をご紹介します。
処分期間が定められている理由
期限を経過すると賦課権が行使できなくなり、税務署は申告誤りを把握したとしても、納税者に対して税金を納めさせることができません。
国税の法律関係において国の行使し得る権利を無制限に認めてしまうと、納税者は法的安定を得ることができなくなります。
国に関しても、国税の画一的な執行が難しくなる側面があることから、賦課権や徴収権などに関しては期間制限が設けられています。
国税当局が税務調査を実施できる期間に制限が設けられている一方で、納税者が納め過ぎた税金を国から戻してもらう、還付請求権についても期間制限が定められています。
還付請求権は原則5年となっており、5年を過ぎてしまうと原則納め過ぎた税金は戻ってきませんので注意してください。
3年の除斥期間
課税標準申告書の提出を要する国税のうち、当該申告書の提出があったものに係る賦課決定(納付すべき税額を減少させるものを除く)の除斥期間は3年です。
一般的に税務調査の対象となる期間が3年と言われているのは、3年の除斥期間の対象になることを根拠としています。
5年の除斥期間
3年の除斥期間の対象となるケースを除き、 更正、決定および賦課決定の除斥期間は原則5年です。
5年の除斥期間の対象となるケースとしては、無申告者に対して実施される調査が挙げられますが、申告書を提出している納税者であっても賦課決定する事由が把握されるようなときは、調査期間が5年に拡大します。
また例外的なケースとして、贈与税の更正決定等は除斥期間が6年と、他の税目よりも1年長く設定されているのでご注意ください。
7年の除斥期間
意図的な虚偽申告や不正計算で税金逃れや、純損失等の過大申告をした場合の更正の除斥期間は7年です。
(10年の除斥期間の適用を受けるものを除く。)
いわゆる脱税に該当する場合の調査期間は7年と、一般的な税務調査より2年長く遡って調べることが認められています。
10年の除斥期間
法人税に係る純損失等の金額を増加(減少)させる更正の除斥期間は10年です。
個人の純損失等の金額に係る更正の除斥期間は5年ですが、法人の青色申告は欠損金を最長10年繰り越すことが認められていることから、除斥期間は最も長い10年に設定されています。
除斥期間の特例
- 除斥期間が終了したとしても、下記に該当するケースにおいては、例外的に更正決定等を行うことが認められます。
- 不服申立てまたは訴えについての裁決、決定または判決に伴う更正決定等
- 経済的成果の消失に伴う減額更正および、当該減額更正に伴う加算税の減額の再賦課決定
- 災害による期限延長等の場合における更正の請求に係る更正
- 国外取引等に関する租税条約相手国からの情報に照らし、非違があると認められる場合の更正決定等
実際の税務調査で対象となる申告書の範囲
国税当局は法律で定められた期間まで遡って調査することが可能ですが、調査を行う目的によっては調査年分を絞ることもあります。
一般的な税務調査の対象期間は3年
事業者に対する税務調査では、3年分の申告書を調査対象にすることが多いです。
3年の除斥期間に該当するのも理由の一つですが、税務署の職員は1件当たりに費やすことができる日数に上限があることから、調査期間を絞る傾向にあります。
ただし、3年以上前に提出した申告内容に誤りやある場合や、無申告となっている事実が判明した際は、3年以上前の申告書を調査対象にすることもあるのでご注意ください。
無申告に対する調査範囲は5年
調査担当者は税務調査を実施したことによる実績も求められていることから、増差税額が大きい事案ほど調査対象となりやすいです。
税務調査は本来納めるべき税金を支払わせることが主な目的ですので、税務署は無申告の取り締まりには積極的です。
すでに申告書を提出している年分については、申告漏れや申告誤りがあった部分のみが増差税額の対象となりますが、無申告者に対して実施される税務調査は、指摘した部分がすべて増差税額です。
したがって、増差税額の発生が見込まれる年分については、法律で認められた範囲全部が調査対象となる可能性が高いです
脱税の疑いがあれば7年前まで遡る
意図的な不正や脱税行為をした納税者については、7年前まで遡って税務調査が実施されます。
不正・脱税行為による金額の大小は関係なく、不正による脱税額が少額であったとしても、その年分の調査期間は7年に拡大します。
脱税は重加算税の対象となるので、ペナルティが重くなることはもちろんのこと、調査が終了した後も税務署にマークされることになるので気を付けてください。
事業を継続している限り税務調査を受ける可能性はある
税務調査を実施できる期間は法律で規定されていますが、実際に税務調査が行われるかは別問題です。
たとえば法人の場合、実地調査が行われる確率は3~4%程度とされていますので、税務調査を1度も受けたことがない会社や、10年以上税務調査を受けていない会社も存在します。
申告書を提出してから5年を経過すれば、基本的には時効が成立するので、その年分の申告書に対して税務調査が行われることはなくなります。
しかし、事業を継続している限り申告書は毎年提出することになるため、税務調査が実施されない可能性がゼロにはなりません。
適正な内容の申告書を提出していれば、税務調査を受ける確率は下がる一方で、税務署は周期的に調査を実施することもあることから、10年以上調査を受けていない会社であっても調査に備えておく必要があります。
税務調査は税務署から事前連絡が入る
調査担当者が自宅や事務所に訪れて実施する調査は「実地調査」といい、実地調査は原則として調査担当者から調査を行う旨の連絡が事前に入ります。
納税者は税務調査の連絡があった後、対象年分の申告書の控えおよび関係書類を用意し、調査対応に備えることになります。
事前通知においては調査日時や対象税目だけでなく、調査対象となる申告年分が伝えられ、通知されなかった年分や税目を調査対象になることは原則ありません。
ただし、税務調査の際に調査対象とした年分以外にも調査を実施する要因が判明した場合や、他の税目に波及することが想定されるケースでは、調査途中で対象範囲が拡大することがあるのでご注意ください。
まとめ
時効になれば不正が摘発されることはなくなりますが、不正を行った事実が税務署に判明すれば、調査ができる年分の申告書は細かくチェックされますし、税務署から徹底的にマークされることになります。
事業者に対する実地調査は3年分の申告を調査対象とすることが多く、法人税については申告書を提出してから半年を経過すると調査が行われやすくなります。
調査対策は時効期間を考えながら練るものではありませんが、知識として除斥期間等は覚えておいてください。