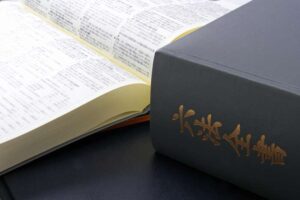税務調査は税金を回収する目的で実施することが多く、基本的には過少申告に対して調査を行うことが多いです。
ただ税金を過大に納める内容の申告書についても調査対象になることはあるため、申告誤りに気が付きましたら、調査の有無に関係なく対処することが望ましいです。
本記事では、申告内容が誤っていた際の対処法と、過大申告に対して税務調査が行われるケースについて解説します。
税金を過大に納めていたときの対応方法
過大申告は提出した確定申告書の内容に誤りがあり、本来よりも納税額が過大となった申告書をいいます。
国税は申告納税制度を採用しているため、納税者が自主的に申告・納税をしなければならず、申告内容に誤りを把握した際も自主的な修正が求められます。
申告期限前に過大申告に気が付いた場合
申告期限前に提出した申告書の内容に誤りを把握した際は、訂正申告書を提出することになります。
訂正申告は期限内に申告内容を修正する方法をいい、訂正申告書は期限内であれば何度でも提出することが可能です。
過大申告による税額をすでに納めていた場合には、過誤納金として納め過ぎた税金が戻ってきます。
納税額が過少だと附帯税が課されることもありますが、訂正申告は期限内に誤りを正す行為であるため、訂正申告で納付税額が増えた際に附帯税を支払うことにはなりません。
なお、期限内に複数の申告書を提出した場合、最も後に提出した申告書が有効な申告として取り扱われますので、訂正申告書を提出する際は申告内容を今一度ご確認ください。
申告期限後に過大申告に気が付いた場合
申告期限を過ぎた後に過大申告に気が付いた場合、更正の請求により税務署に対して申告内容の訂正を求めることになります。
請求書を提出できる期間は原則法定申告期限から5年以内で、期限を過ぎると更正の請求を行うことはできません。
税務署は提出された請求書の内容を調査し、請求内容が正当と認めた場合に減額更正を行い、納め過ぎた税金が還付されます。
<更正の請求の対象となる主なケース>
- 納付すべき税額が過大であるとき
- 純損失等の金額が過少であるとき
- 還付される金額が過少であるとき
納税額を過大に申告した場合の問題点
過大申告は税金を払い過ぎるだけでなく、税務調査を受ける確率が上がる要因にもなるので注意してください。
過大申告が起こる要因
過大申告をしてしまう主な要因としては計算ミスが多く、事業者については売上や経費の計上時期を誤ることで納税額が過大になるケースもあります。
税金面において、納税者が過大申告を行うメリットはないです。
ただ一部の事業者については、金融機関から融資を受けるために経営状態が良好であると見せかける目的で、意図的に過大申告を行っているケースも存在しますが、推奨される手段ではありません。
税金を余分に支払うことになる
過大申告の最大のデメリットは、税金を余分に支払うことになる点です。
税務署は過少申告に対しては積極的に税務調査を実施し、本来納めるべき税金を回収しようとします。
税務調査で申告誤りを指摘され、修正申告書等を提出することになった場合、本税だけでなく加算税・延滞税も納めることになるため、適正に申告したときよりも負担が重くなります。
一方で、過大申告は税金を多く納めている状態ですので、税務署は申告誤りを指摘したとしても基本的に税収は増えないことから、過大申告を指摘することには消極的です。
申告期限を過ぎたから過大申告を訂正したとしても還付金が減ることはありませんし、加算税・延滞税の対象にもなりません。
ただし、過大申告を放置している状態は税金を余分に納めているのと同じですので、気が付いた時点で更正の請求書を提出するなどの対処が必要です。
更正の請求が認められない可能性がある
期限後に申告内容の誤りに気が付いた場合、納税者が自主的に更正の請求書を提出することになります。
更正の請求書は修正申告書とは違い、税務署が請求内容を認めた場合に限り申告内容が修正されるため、更正の請求が却下されてしまうと払い過ぎた税金は戻ってきません。
また更正の請求書には申告内容に誤りがあった理由だけでなく、更正の請求をするに至った根拠も示さなければならず、請求内容に応じて書類添付も必要です。
税務調査の対象となる可能性が上がる
税務調査は申告内容を正すために実施しますので、申告内容に誤りがあれば過少申告・過大申告を問わず、税務調査が実施される可能性はあります。
過大申告は税金を払い過ぎている状態であるため、税務署が積極的に調査を行うことはありませんが、税務署が過大申告となった以外の部分の誤りや、申告漏れの事実を把握していることもあります。
申告内容に誤りが多い場合、意図的に申告内容を偽っていることを疑われることもあるため、過大申告をしていれば調査を回避できるわけではありません。
過大申告に対して税務調査が行われるケース
過少申告に比べれば税務調査が実施される確率は低いですが、次に該当する場合には過大申告であっても調査対象になることがあります。
申告誤りが翌年以後の申告に影響を及ぼす場合
税務調査は申告が適正に行われているかをチェックするものであり、過大申告も申告誤りの一つです。
過大申告は納税者が多く税金を納めている状態ですので、税務署も申告誤りを把握しながら放置するケースもありますが、事業者の場合には申告誤りが翌年以後も続くことが懸念されます。
計算ミスや法令解釈の誤りが過大申告ではなく過少申告になることも想定されることから、税務署は翌年以降に適正な申告書を提出させるために、過大申告であったとしても税務調査を実施することがあります。
申告内容全体に疑義がある場合
申告書の複数の箇所に誤りがある場合、誤りをすべて是正することで過大申告から過少申告に変わる可能性があるため、申告内容自体に疑義があるときも調査対象になりやすいです。
意図的な税金回避を指摘されないために過大申告を装っている納税者も存在することから、赤字申告や過大申告に対しても税務調査は実施されます。
税務署の立場からすると、結果的に他の部分の申告誤りが判明しなければ納め過ぎていた税金を戻すことになりますが、申告書を適正な内容に直しただけなのでマイナスにはなりません。
他の年分の申告書と合わせて調査対象になる場合
事業者は毎年申告書を提出することになるため、他の年分と連動することも少なくありません。
他の事業年度の売上を計上している場合や、本来経費計上できる金額を他の事業年度の経費にしているのであれば、すべての申告書を確認しなければならないため、過大申告をしている年分も調査対象となります。
また、税務調査は複数年分をまとめて調査するのが一般的ですので、他の年分への影響がないとしても調査対象になることはあります。
まとめ
過少申告の方が確率的には税務調査の対象になりやすいですが、過大申告も調査対象になる可能性はあります。
税務署は申告誤りの金額が大きければ、次回以降に提出される申告書を細かくチェックするようになりますし、要注意人物としてマークされると調査を受ける確率は上がってしまいます。
税務調査は不正申告を抑制するための牽制目的で実施することもあるため、税務調査を可能な限り回避したいときは、適正な申告書を提出することがベストな選択です。